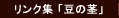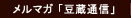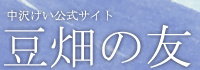 |
||||
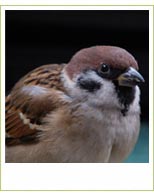 |
| タイトル一覧 |
| 最新の10件 |
| 伊藤比呂美Twitter |
| Twitter三匹の子豚リスト |
| ログ検索 |
| 年譜 |
| 著作リストへ |
| 管理者用 |
|
NYから出た 2014年05月30日(金) 時差ぼけの時差ぼけで、前々夜は夜明かししてしまい、そのかわりに朝から午後の2時すぎまで寝たのだが、前夜もまた。寝なくちゃと思ってとろとろ寝入ったけど、1時間も眠らずに目が覚めて、また夜明かしだ。朝は7時半には出ようと思っていたので、いっそのことと思って夜明かしのまま、6時半にホテルを出た。で、最寄りの地下鉄から地下鉄カード買って、地下鉄に乗ったのはいいが、51ストリートで降りてレキシントンに乗り換えというのを、レキシントンで降りて乗り換えというのに思い違えており、いつまでたってもレキシントンにつかないので、メモを見たら、間違いに気づいた。それで降りて乗り直して51で降りて乗り換えて、さらにエアトレインに乗り換えて空港についたのである。すごい冒険であった。二つ目のE線はがらがらで、かばんから本を出そうとしたら、手元のケースが高速でがらがらと動いていってしまった、それを足でキャッチしてくれた男が、なんとまあいい男、濃い顔がすっきりとして、中東系かというような、あたしはにこりとしてお礼をいい、男もうなずき、男が降りるときにも目があったので、またにこりとしあって、いや……すごい冒険であった。 朗読おわった 2014年05月29日(木) PoetryProjectの朗読@St.Marks教会はおわった。ふーーー。演目は「カノコ殺し」を日本語で。「新訳般若心経」を英語で。「ヤキソバ」を英語で。案の定PowerPointがうまくつかえなくて、たまたま来てくれた日系のYくんとKさんにずいぶん助けられた。終わった後、同年配の女の詩人たちとワイン飲んで、フムスとフレンチフライ食べた。ちょーおもしろかった。ま、来てよかったのかもしれないな。←いつもいやいや出かけて、いつもこう思う。素直なんです。 忘れ物 2014年05月28日(水) 時差ぼけの時差ぼけで何がなんだかわからなくなって、夜明かししてしまって、外は明るくなり、車が行き来し、人々が歩いたり走ったりしており、おなかはぺこぺこ。今回また忘れものをして(旅のたびにいつもする)それはここんとこ手放さずに読んでいた「文語訳新約聖書」。おもいっきり読めると楽しみにしてたのに、忘れてきた。飛行機のなかで、かばんに入ってないのに気がついたときには自分をのろった。持ってきたのは自分の詩集と「説経集」と「日本霊異記」だ。しかたがない。「説教集」の解説を粛々と読んでいる。タメになる。おなかすいた。でもそろそろ寝ないと。 NYについた 2014年05月28日(水) 深夜のNY。イーストヴィレッジというところの安ホテル。この近所でPoetry Projectという朗読会シリーズがあり、そこに呼ばれている。Poetry ProjectのあるSt.Marks 教会の住所と「ホテル」をgoogleに入力したら、最初に出てきたのがこのホテルだったというわけだ。しかし見るからに安ホテル。わかーい頃、前夫と旅行したパリの安ホテルなみの安ホテル。支払いは現金のみというので、あわててATMでお金をおろした。ネットも別料金。受付のおにいさんの声が小さくて3回くらい聞き直さなければわからないとこも、ほんとに安ホテルっぽかった。部屋は、迷路みたいに階段をのぼったりおりたりして行き着いた先で、火事でもあったらここが死に場と思いながら、案内のおにいさんについていった。部屋には机もない。バスタブもない。まんがいちと思ってシャンプーとリンスもってきといて正解だった。大きな鏡があって、すすけたラジエーターがある。窓には木枠と木の扉が嵌っている。雰囲気だけはある。何か起こりそうではある。外は荒天で、かみなりが鳴ったり風が吹いたりしている。周囲には24時間営業のベーグル屋とかがある。出迎えてくれたAは、名前からすると、太った髪の毛が肩まであるようなおばさんかと思っていたのだが(この人の熱意にほだされたのだが)小柄でやせた、14、5歳の男の子たちみたいなレズビアンカップルの一人だった。ちょー感じイイので、たちまち気を良くして、あしたがんばろうと思ったのであった。でも客の入りはわからないそうだ。英語使わない詩人も、Aが担当しはじめてからは初めてなんだそうだ。 ぐちをこぼす 2014年05月27日(火) きょうNYにいくのですごくすごく気が重い。呼んでくれた人の熱意にほだされてついOKしてしまったがほんとにほんとに行きたくない。呼んでくれた人たちはどうせ日本語なんか読まないだろうし、こんなブログも知らないだろうからぶっちゃけて言うが、ほんとに気が重い。30分かそこらの朗読するのに3日使って、空港で辛い思いして、出かける意義がわかんない。しかも行き来に使う航空会社はUSAirwaysで、いつものUAじゃなく、ついこないだスターアライアンスから脱退したという。それで空港のラウンジが使えない。とっても不快な数時間をフェニックスかどこかで過ごすのだ。待ち時間がやたらに長い。きのうはトメに英訳を表示するPowerPointを作ってもらった。前自分でやったら、2つ作るのに3日かかったから、今回はトメに下請けに出したのである。とにかくJもいない、一人でやるしかないのでよけい不安。車で動けないからさらに不安。知らない大都市はだいっきらいだ。仕事多すぎて、遊んでるひまはないし、遊ぶつもりもない。一人旅がそもそもきらい。旅そのものがきらい。知らないとこに行くのがきらい。芭蕉も西行も誰ソレって感じ。せめて音楽だけでもと思い、ずっとほしかったKeenlysideの出ているCDを2,3枚買い込んでiPodに入れた。しかしそのiPodもむかーしのclassicだから、すごーく重くて使いにくい。トメのは新しいからちょー軽くて使いやすい。うらやましい。もういい加減ねないと。 時差ボケと聖書 2014年05月26日(月) 日本に1週間しかいなかったのに、しっかり時差ボケておる。夜(宵の口)猛烈に眠くなり、眠りこけ、真夜中に起きだして今に至る。朝は犬に起こされるのでいやいや起きて、ズンバやってるうちに紛れ、午後また猛烈に眠くなり、泥のように眠りこけて夕食前に起きて、ないしは犬に起こされて、ごはんを作って食べる。というスケジュール。ここ数日、夕方のズンバがないか、Mが教えてないから行かないかで、夕方はリラックスしていたのである。 ありのままの 2014年05月26日(月) Frozen、つまり「アナ雪」が、ダブル女主人公というのが話題になったそうだが、ダブル女主人公なら、「トトロ」も「ナウシカ」もそうではないか。1人の人格の裏表という面でも。「いい子」からの逸脱という面でも。って、みんな言ってることかしらねー。 『瞼の母』 2014年05月25日(日) 日本で買った本の中に小林まことの『瞼の母』がある。長谷川伸シリーズの完結。いやーーーよかった。結末を変えてある。うちの母も『瞼の母』が大好きだった。その結末に、ものすごく悲しい思いをしながら、それでも感動して、もだえ泣いていたはずだ。母がこの漫画を読んだら、結末に、違うと思いつつも、ああ、でもこうなってほしかった、この結末を読むのが夢だったと、心の底から思ったはずだ。主役は東三四郎、脇役では森の石松役の千代崎がよかった。このシリーズの『沓掛時次郎』、雨竜光二という比較的マイナーな役者が主演だったが、絶品だった。この小林まことの『瞼の母』と『沓掛時次郎』の話をY折先生にしたら、「家族の話なんだ、震災以来、家族の話がもとめられているんだ」とおっしゃっておられた。なるほどーーー。 逃避…聖書のことば 2014年05月24日(土) 前々回の日本行きで、岩波文庫の『文語訳新約聖書』をかひもとめ、昔、初めて読んだ聖書というのは父の持ってたやつだから、たぶんコレ。で、読んでいるうちに、このことばはどこから来ているものかものすごくものすごく気になったのである。なんか違う、江戸とは違うし、鷗外とも違う。鴎外の翻訳のことばがどこから来ているのかもずっと気になっていたけど、聖書はもっと古い。そしたらこないだベイエリアで、Jが『聖書の日本語』(岩波書店)という本がおもしろいと教えてくれた。それで今回の日本行きで買ってきた。で、鴎外そっちのけに読んでるがすごくおもしろい。最初の「明治元訳」(1879年に翻訳しおえた)は中国語訳聖書からの影響とともに、『親鸞聖人御一代記』『童蒙をしへ草』(福沢諭吉訳1972年)と貝原益軒(1630-1714)の文章をモデルにしたんだそうだ。親鸞聖人御一代記はみつけられなかった(蓮如の一代記はみつかった)、をしへ草はみつけた、でも他の福沢諭吉(1835-1901)をいろいろ読んでみると、『西洋事情』(1866〜)『学問のすすめ』(1872)おおっコレコレというような明治元訳聖書の日本語への近しさを感じるではないか。諭吉は、明治初期ないしは江戸末期に共通する話し言葉的書き言葉を使ってたのかもしれない。諭吉による造語もいっぱいあるようだ。鴎外より27年も早く生まれて、もっとずっと早く外国語と格闘し始めた人だ。鴎外、黎明期とばかり考えていたが、諭吉はもっともっと暗闇の中だった。ああ、あたしもこの時代に生まれたかった。手探りでことばを作り出す。この時代の人たちはみんな明治元訳聖書みたいなことばでものを書いていたのかもしれない。他に誰がと考えたが、龍馬は青空文庫に入ってない。勝海舟はくだけすぎている。榎本武揚どうかと思って青空文庫をさぐったら、なんと鴎外の本の跋文書いてるが、漢文だったーーーーー。てなことしてないで、さー仕事仕事。 カリフォルニアに帰った 2014年05月23日(金) とはいうもののLAXで待ち時間が長くて睡魔とたたかいながら待っている。仕事する気になれないし。Nちゃんちで読書用のメガネを踏んで壊してしまったので、本読むのがちょっとつらい(でもまあ読める、コンピュータ用のメガネで)。頭のなかで、機内で見ていたFrozenの「れりごーれりごー」が鳴り響いている。 ページ移動 / [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||