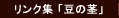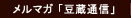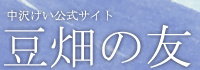 |
||||
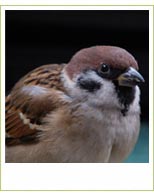 |
| タイトル一覧 |
| 最新の10件 |
| 伊藤比呂美Twitter |
| Twitter三匹の子豚リスト |
| ログ検索 |
| 年譜 |
| 著作リストへ |
| 管理者用 |
|
2月4日「比呂美の部屋学園ライブ」加納良寛氏の巻 2014年02月01日(土) すぐじゃん。 2月11日「語り合えば万事OK」 2014年02月01日(土) 「ライブ万事OK+語り合えば万事OK」 2月8日「声のライブラリー」 2014年02月01日(土) また忘れてました。すごく大切なこと。 発見…いまさら 漫画 2014年01月29日(水) 「スターシステム」を検索していたら手塚治虫のロックに行き当たり、そういえば、ロックってヨハンみたいって思ったら、「バンパイヤ」が読みたくなり、さっそく買って読んでみたら、なんと「下田警部」がリヒァルトだった。そして「バンパイヤ」でも、下田警部が殺されて、ヒゲオヤジが立ち上がるのだ。そして読んでみたら、ほんとにロックはヨハンだった。てなことはみんなもうわかってるんでしょうが、あたしは今ごろ気がついた。これはサンデーでさんざん読んだが、あんまり人が殺されるので、いやになってそのあと読まなくなったような気がする。11歳の頃だ。サンデーは学校でだれかのを借りて読んだ、はず。出だしのかっこよさはその頃わからなかった。今みると、ぐいぐい引き込まれる。 雨乞い 2014年01月27日(月) 隣の荒れ地のセージたちが枯れている。花は咲き始めているが極端に少ない。いつもはいちばん早く咲くジンコウザクラが咲いていない。 尋ね人 2014年01月26日(日) 尋ね人に無事につながってうれしいのである。その上、ゆうべ空から水滴が。ほんの少し。こういうのはrainingとは言わない。spitting(つばをはく)という。 F永Y子さん 2014年01月24日(金) F永Y子さん、もしこれを見ていたらご一報を。どうぞよろしくお願いいたします。 パトレイバー 2014年01月24日(金) こんどの読売のビタミンブックは「シュトヘル」について書いた。たしか26日頃だ。字数がないから西夏文字のことしか書けなかったが、女の肉体に男の心が宿るっていう設定の妙についても書きたかった。もちろん探せばもっとあるだろうが、すぐ思いついたのがゆうきまさみの「鉄腕バーディー」、漫画の世界ってほんとにいろんなところから声をお借りして成り立っているのだなと感心する。で、ゆうきまさみといえば、「パトレイバー」だ。「バーディー」も人間の世界は悪くはないが、宇宙人がごちゃごちゃしすぎている。やっぱり「パトレイバー」だ。で、この絵も設定も小道具もいかにも80年代な「パトレイバー」の醍醐味は、まるで実写映画(しかも名優を金に糸目をつけずにキャスティングしたような)のような顔とキャラの描き方のリアルさなんである。ここには「MONSTER」の人情話に感じたような人間関係話の既視感は感じられない。もっと漫画だからできる表現をめざしている、んだと思う。主人公たちは漫画的な処理をほどこされて、ああいう顔でああいうキャラだ。しかし脇役たちは、実在の人間をモデルにしているように多種多様でおもしろい。好きなキャラは、内海課長や後藤課長、黒崎さんやシゲさん…といろいろいるけれども、いつも、いいなあと見入っちゃうのが、警視庁かどこかの会議で、まじめな顔して「作戦名に提案のある方」などと司会する人だ。それから帆場さんといったか、シノハラかどこかの技術者で夜遅くまで働いている人(ひとコマしか出てこない)。ロボット漫画といってもいろいろあるが、ガンダムなんかが戦車みたいなものからの進化形で、アトムとかがヒトからの進化系で、鉄人28号なんかはリモコンおもちゃからの進化形で、山本さんちの息子(ひさうちみちお)が扇風機(アレ? トースターだったっけ?)からの進化形としたら、パトレイバーはヤンマーとかクボタとかの農業機械や建設機械たちからの進化形なんである。そこもすごい。 のだめ 2014年01月24日(金) 「のだめカンタービレ」はおととい読んでた。パリにいくまでは夢中になって読んでいたが、音楽漫画といえばくらもちふさこの往年の「いつショパ」だったけど、そんなのメじゃないくらい(いや、くらもちふさこ、大々々好きなんですが)、音楽がたんに背景や小道具として使われるんじゃなく、音楽が音楽として全面に立ち上っている、うんちく漫画の最高峰の一つ、として評価してたんだが、パリにいってからの話はてきとうに読んでいたのであった。そしたら、おととい、20とか21とか22とか23巻とかを読みかえしてみたところ、こんなにすごかったのかと自分の読み方を反省した。千秋の役割やシュトレーゼマンの役割、Ruiの役割も、うまくきちんとはまりこみ、それがいちいち音楽ときっちり結びついておる。まるでジグソーパズルのような(別にこないだやったからこの比喩を出してきたわけじゃない)快感を感じつつ、大団円にむかったのである。シュトレーゼマンとファウスト(のメフィストフェレス)が重なるところなんかぞくぞくした。しかも千秋よりのだめのほうが、天才、成功、という話のもっていきかたに、とてもとてもとてもとても好感を持った。 MONSTER 2014年01月24日(金) 読む漫画が尽きたので古いのひっぱり出して読んでおる。きのうは浦沢直樹の「MONSTER」すごい漫画で何度読んだかわからない。2000年前後に読んでいたときは、読みながら、ライヒワイン先生がヒゲおやじというのに気がついて、天馬博士や日本人のもぐり医者やケン一のもじりのケンゾーや、なんかいろんなところで手塚漫画から声をお借りしてるのに気がついて震撼したものだ。あたしはもともとチェコの絵本にはけっこう詳しかったから、浦沢直樹がチェコ語で絵本をつくっちゃったのにも驚いたし、会話の一部が訳なしのチェコ語なのにも驚いたものだ。そういう感動はまだ持ってるのだが、きのう読んでいたら、これだけじゃなくて、キートンにも感じていた「すごいな、人情話を描く職人芸だな」という感想が「既視感」ということばに集約されていくのを感じた。つまりここに描かれる人情話は、いつかどこかで見た(ないしは読んだ)人情話、そしてそれを見た(読んだ)ときの感動を、繰り返そうとしているのだということに気がついた。そこにあるのは漫画だからできる表現というより、映画の、テレビの、小説のひとこまの上質ななぞり、漫画化である。のではないか。 ページ移動 / [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||