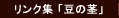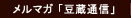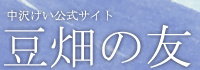 |
||||
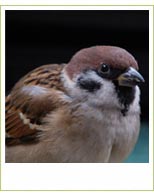 |
| タイトル一覧 |
| 最新の10件 |
| 伊藤比呂美Twitter |
| Twitter三匹の子豚リスト |
| ログ検索 |
| 年譜 |
| 著作リストへ |
| 管理者用 |
|
ボウモアの町 2014年04月10日(木) 朝、出発前にボウモアの町を歩きまわった。崎津の天主堂のある町よりも小さい、何十年も、もしかしたら何百年も、なにも変わらないんじゃないかと思わせる、ひとつひとつの有機体は生き死にをくりかえしても町そのものは何もかわらないんじゃないかと思わせる町だ。ピアの突端にすわってしばらく入り江の向こうをながめ、町をながめ、波の模様をながめていた。雲が流れ、陽がさしていた。それから町を歩き回った。いくつかのレストランや宿屋も、co-opのスーパーも目医者も獣医も歯医者もみやげものやも、ガソリンスタンドも、白い四角い家々の中にひっそりと在る。うらんかなとか目立とうとかの意識はあんまりないみたいだ。ボウモアの蒸留所が町の経済の中心に違いないが、それも同じような白い四角い建物で海際にへいぜんと建っている、それがそれだとわかるのは海に面して白壁に黒字で書かれたBowmoreの字ばかりだ。町の小高いとこに教会があり、Church of Scotlandで、裏には墓地があり、War graveとかいてあって、Two sailors, A sailor, A flying officer, などと書いてあった。39-45と書いてあった。流れ着いた遺体を葬ったんじゃないかと考えた。それはふつうの墓石だったが、むこうのほうにはケルト風の円の中に十字のある墓石がいくつも立っていた。 鹿肉 2014年04月10日(木) 夕食は鹿肉をたくさんのカルダモンとネズの実で煮込んだものにLagavulin(アイラ産シングルモルトの一つ)をかけて焼いたものを、ホテルのお兄さんにすすめられて食べた。つれあいはハドック(コダラ)の燻製のワインとクリームのソースがけ。うまかった。このホテル、部屋はみすぼらしいが料理はうまい。鹿肉、初めてだと思う。こないだ『山賊ダイアリー』を読んでいたのだ。あれはおもしろかった。漁師になった男のエッセイ漫画である。カラスを撃って殺して解体して料理するところも、鹿を撃って殺して解体して料理するところも、如実に描いてある。 動植物 2014年04月10日(木) まず朝はCaol Ila蒸留所に行ったが、ツアーはお休みで酒だけ買った。それから島を北端まで、行こうとしたが途中で道が切れた。それから南端まで走り抜けた。途中Finlaggan。Askaig。Portnahaven。Mor。これは地名だが、みんな『オシアン』に出てくる人たちみたい。けっきょく走り回っただけで、夕方Bowmoreのホテル着。ビールのんで、食堂で仕事していたら、ホテルのおにいさんに話しかけられて話しこみ(若い人だからか、60%は理解できた)いろんな話を聞かせてもらった。それは今「honto」に書いてるので。 朝食のハギス 2014年04月09日(水) この小さなホテルの朝食は、卵2こにベーコン2枚、ソーセージが2本に煮た豆、ブラックプディングにハギス。それはつれあいので、あたしはそんなに食べられないというと、卵1こにベーコン1枚を作ってくれた。とにかくハギス。食べてみたかったもののひとつだが、食べられるかどうかわからず、というのもあたしの苦手なものの一つに動物の内臓や脂肪があるからで、つれあいのを少しもらった。今どきの出来合いハギスで、まわりはプラで、胃ではなかった。中身は、ほとんど脂肪とスパイス、ハーブと穀物で、たぶん内臓の極細ミンチもまじっていたはず。ヒツジの肉は嫌いだが、これは気にならずに口に入った。しかしおいしいかと言われれば、むずかしいところで、脂肪の多さは閉口した。ある意味、北米先住民のペミカン(細肉やナッツ、ベリーを脂肪で固める)やポーランドのスマレツ(りんご入りのラード)に似たものかも。黒プディングはポーランド料理のカシャンカと同じ、血を穀物に混ぜたもので、もちろん苦手である。 生牡蠣にスコッチに幹郎さんの本 2014年04月09日(水) 幹郎さんに勧められたのが、生牡蠣にシングルモルトを滴らせて食べるというもの。さっそくホテルのレストランでみつけた。注文とりにきたホテルの人に、友人に勧められたと言うと、このへんではそうやって食べるんだ、と(言ったそうだ、つれあいに通訳してもらった)。頑固で保守的なつれあいはそんなことをしたら生牡蠣の味をスコッチが殺し、スコッチの味を生牡蠣が殺すはずだといってきかないので、あたしだけ注文してみた。そしたら来たのが、牡蠣にほんとにスコッチだけ。そしたらウマいのなんの。あたしはスコッチは飲まないというか飲めない。一滴も飲めない。それなのに生牡蠣の塩気の効いた冷たいおつゆに混じり合ったスコッチはぜんぜんいやじゃなかった。すごくウマかった。また食べたいが、さすがにこの島でしか出ないと思う。来る途中の機内でIslay祭りの一環として、岩波新書の『東北を聴く』(佐々木幹郎)を読んでおった。すごくいい本だった。 Islay島 2014年04月09日(水) 10日間暮らしたSohoのアパートメントからロンドンシティエアポートに行き、空港内のレストランでOld speckled henを飲みつつ、グラスゴー行きの飛行機に乗り、グラスゴーについて、こんどは小さい、小さい、小さい飛行機でIslay島に。車借りてBowmoreの町のホテルに。よそのところが取れなくてここになった。ちょうど崎津の天主堂のある漁村みたいな小さい村の小さいホテルである。グラスゴーについて驚いたのは人のしゃべる言葉がぜんぜんわからないことだ。ロンドンのタクシーの運転手さんたちのコックニー弁もわからなかったが、ここはさらにわからない。これがあの有名なスコットランド弁というものかー。まったくわからない。英語じゃないみたいだが、こっちの言うことは通じるし、つれあいは聞き返しながら(耳が遠いせいもある)会話している。あたしはほんとにわからない。「あい」といってみんなうなずく。「いえす」らしい。Islayは、アイレイじゃなくてアイラと読むらしい。 ベイカー通りとライラック 2014年04月08日(火) はらはらしながら郵便を待った。通常郵便は来たのに、あたしのは届かず、焦って郵便局に問い合わせたりしていたが、昼前になってやっと速達配達専門の人が来た。呼び鈴が鳴ったときにはどれだけほっとしたことか。それからJとNの家にいったが、行きに、タクシーの運転手に、Baker Street 221Bを通ってと頼んだら、ちゃんとその前を通り、ゆるゆる徐行してくれた。おまわりさんがいて、人がたくさん並んでいた。思ったより広い通りだった。思ったより広いと言ったら、親切な運転手さんがいろいろと説明してくれたが、ものすごいコックニー弁で、何いってるのか皆目わからなかったのである。すずめのチープサイドは、もしやこんなことばをしゃべるのではあるまいかと考えた。JとNに向かうと、つれあいが因業なじじいというより、ただのなまいきな男の子みたいになる。 寝てない 2014年04月07日(月) 仕事が終わらなくて根をつめてやっていたら、寝そびれてしまったのである。根をつめてといってもあたしの場合、YouTubeでなんかききながら(そういうことは勉強中はやめろと、いつも娘にいってるのに、けっきょくおんなじことをしておる)で、どうにもオペラにハマっていろんなものを聞いてしまう。あれこれあれこれ聞いてるうちに、どんどん広がって、こないだ亡くなったロバート・アシュリー(ご冥福をお祈りします)やフィリップ・グラスなんかも聞いてるうちに、なんかむらむらとしてきて、ついに作曲家のFさんにメールして、ねーねー、オペラやろうと持ちかけてしまった。Fさん、すてき、打てば響くようにのってくれた。ほんとにそんなことできるものなのかどうかもわからない。でもこうやっていろんなこと思いつくから人生は楽しい。寝てない理由のもう一つは、カリフォルニアに免許証忘れてきてしまって、Sに送ってもらったのであるが、なかなか届かなくてはらはらしているのであるが、今日くらい来るかもしれない。つか来ないと困る。郵便屋さんが呼び鈴鳴らしたら、ぱっと出て行かないとと思っているうちに寝そびれた。いったん横になったのだが、寝つく前に何か読む習慣だ。きょうはついにここのところ読んでいた『森鴎外 文化の翻訳者』(長島要一)を読み終えた。数年前に出た本だが、諸般の事情で読み返そうと思って持ってきて読んでいた。これがおもしろくてたまらず、つい頭が興奮してしまって寝そびれた。数年前に読んだときもとても興奮して、自分は自分であるとカウンセリングにかかったような快感というか治癒感を覚えたものだ。いや、表題のとおり、鴎外の本であってカウンセリングの本じゃないんですけど。それから続けてこれも読みかけの『和音羅読』(高橋陸郎)を読んでたらカトゥルスのあたりでやっぱ興奮してきて、それでも寝そびれた。とにかく睡眠不足ハイな感じ、今日は郵便屋さんと会って、つれあいの友人夫婦と会って、夜はレストランにいくだけで、コンサートもなけりゃ運転もしないから、睡眠不足でもOKなんである。 つれあいと向かい合って仕事 2014年04月07日(月) せっかく仕事机が二つあるアパートメントを借りたというのに、食卓で仕事しているあたしのそばにつれあいがコンピュータをもってきて仕事を始めた。食卓は大きいので、居心地がいいとみえる。あっちいけとはいえないし、あたしのものはあたりいちめんに放り出してあるのであたしが動くこともできず、向かい合ってもう数時間。あたしはなかなか集中がつづかずに、YouTubeで音楽きいたり、なんか検索したり、メールしたり、ブログかいたり、貧乏ゆすりしたり、水のんだり、チョコ食べたり、ときに踊ったりしてコマ切れに仕事するのだが、つれあいはがーっとやっている。小さいラップトップの上におおいかぶさって、ぶっとい指でうちにくそうに打っておる。ラップトップ使いにくいといって、わざわざマウスを持ってきたけど、結局使ってないようだ。コンピュータの専門家のくせに、ものすごく使い方の要領が悪いので、家族はいつも笑っている。でも今は、自分のプログラムをなんかしているらしく、要領のいいわるいや指の太い細いは関係ないのだと思う。昔、カリフォルニアに来たばかりのとき、彼の仕事机のとなりで仕事していて、その集中度がうっとうしく、息が詰まるようで、別の部屋に仕事場を作って離れたのである。ひさしぶりに見ていると、前より集中度が気にならない。慣れただけかも。ときどき、「あっ」とか「はっ」とか声を出して驚く。首を左右にふったり、顔をしかめたりもする。どうかしたかと最初は聞いていたが、もぐもぐ答えているつもりでことばにならないで、また集中していく。足腰はこんなに衰えて10メートル歩くのがやっとで、全身の関節はつねに痛んでおり、身動きするたびにため息をついているというのに、こうしてみると上半身の動きはあんまり変わらない。性格も、前からもってる因業さはさらに濃縮されて、物忘れと攻撃性は強まっているが、まあ本質的には変わらない。さぞやもどかしいことだろう。どんどん見えなく聞こえなく動けなくなっていく自分に向かい合うということは。そして死がすぐそこにあって、とりあえず健康体でいながら、つねに「おれが死んだら」と考えねばならない、しかもかなり具体的に、ファンタジーとしての「死」ではなく。(あ、読んでくださってるかたがた、コレ、なんかのためのメモ書きなので、どうかお気になさらず) 犬たちとヒイラギたちと朝コンサート 2014年04月06日(日) 何が不便といって、ロンドン、国際時間の感覚が違う。とんでもない時間に日本の人たちが起きてたり、さっきまでやりとりしていたカリフォルニアの人たちがぱたっと黙ったりする(寝たわけだ)。カノコのところに預けてきたルイとニコがいまいち適応できなくて、はらはらしている。カノコも困っている。ルイの方が不適応が甚だしいらしい。吠えて困るといっていたがそれは前からで、つれあいの耳が遠いのとあたしは慣れてるのとで、気にならなかっただけだ。不適応は、それだけ頭がよくて複雑なせいだとみんなが言う。かわいそうなニコ、あんなにかわいいのに。そして実はけっこうかしこいのに。Sが、もしカノコからSOSでたら迎えにいくといってるが、どうなるか。Sも今は家を離れてアパートに住んでいるので、そこじゃ犬2匹引き取れないし、トメの寮でも無理だろう。ああ頭がいたい。 ページ移動 / [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||