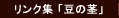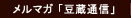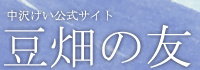 |
||||
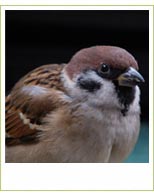 |
| タイトル一覧 |
| 最新の10件 |
| 伊藤比呂美Twitter |
| Twitter三匹の子豚リスト |
| ログ検索 |
| 年譜 |
| 著作リストへ |
| 管理者用 |
|
マーマイト 2014年04月22日(火) イギリスの片田舎のJの家でみんなで食べた、イギリス名物マーマイトを塗ったトーストがとてもウマかった。また食べたくてしかたがないが、イギリスの食料品ばかりおいてあったイギリス屋(仮名)は数年前に閉まってしまい、アジア物がわりと豊富なRalph'sという大型スーパーにもなく、Trader Joe'sにないのは知ってるし、Sproutにあるとは思えないので、今日はWhole Foodsにいってみたのだが、ジャムの棚にもソースやしょうゆの棚にもスパイスの棚にもなかったのである。あとはイギリス人のCに入手先をきくしかない(前にCの家でマーマイトを見た)、ないしは来週ベイエリアにいったとき、カノコの家の近くのヨーロッパ食品専門店で買うか(前にそこでイギリス名物のゴールデンシロップを買った。カノコは父の日とかクリスマスとかにそこでイギリス名物のマーマーレードとかを買って、つれあいに送ってきてくれる)と思いつつ、Amazonいったらあるじゃないの。さっそく注文したのである。どんなものかというと、どす黒い、タールみたいな色と形の、しょうゆを煮固めたようなものだ。何よりすごいのは、発酵臭がすることだ。ぬったりとぬってもなかなか伸ばせないが、最初にバターをぬっておくとよく伸びる。しょっぱい上にしつこいので、あんまりたくさんは塗らない。少しだけでいいのである。これもまた、他の多くのものと同じように(フィッシュ&チップスやシリアルや煉瓦の建物やお酒のジンや……)イギリスの産業革命で需要がのびて、工業化で、大量生産が可能になって、広がったものだ。つまり都市部に流れ込んできた大量の労働者が、かんたんに食事を摂るためのチープな食材。 イースター 2014年04月21日(月) きのうはズンバに2回行った。からだは案の定なまっていた。1回めは8時半でCだが、Cは休みでかわりの人が教えた。エアロビっぽい動きをする人で、今いちおもしろくなく、これなら犬を散歩につれてったほうがよかったなあと思いつつやって、犬を散歩につれていって、12時のM。やっぱMはすごい。おもしろいもへったくれもなく、動かされてしまうのである。Mはもうすぐ自分のズンバ道場を持つのでいつもよりさらに気合が入っていて、それがみんなにも伝わって、みんなが雄叫びをあげていた。そしてあたしはときどき息が切れた。今日は犬を洗ってのみよけの薬をさした。もう咬まれてあちこちかゆい。その上、2匹ともユーカリの花殻を全身にこびりつかせて、家中にこぼし歩いておる。世間はイースターで、きのう(土曜日)から、近所のルーテル派の教会には「イエスがライジング」というのぼりがたっている。きょう(日曜日)は人の出入りが多いから、犬たちは夕方まで散歩につれていかない。小さい子どもがいないとイースターもなんとなく過ぎる。ちょっと前はパスオーパーだったが、つれあいはそういうことに何の興味もなく、毎年なんにもしない。 かへりまひた 2014年04月19日(土) 犬はすごく喜んだ。 ケイ・スカーペッタとエルマーのぼうけん 2014年04月18日(金) ケイ・スカーペッタとクラブケーキの話、東京の友人Aさんから、その蟹料理のところがすごくよかったけど、ケイがいきなり若返ったのに憤慨してそれっきり読んでないというメールが来た。まさに昨日、愛読者だったというCとその話をしていたのである。ほんとうにあれは噴飯物だった。それまでのケイの物語は、アメリカに移住したばかりのあたしに、どれだけアメリカでの女の生き方とアメリカの現実を教えてくれたかわからない。残念である。ケイの老後を、アメリカの女のすさまじい老後をじっくり読んでみたかった。 旧友と蟹ケーキ 2014年04月18日(金) つれあいの学生時代の友人は、つれあいと同じくらいの年頃の女で、夫も同じくらいの老人だった。待ち合わせたレストランについてすぐ、つれあいはトイレに駆け込んでいき、あとからCとあたしが車から出たところ、少し向こうに停めた車から出てきた小柄な、白髪の、脚のわるそうな高齢の女がこっちをじっとみつめているのである。××ですか? ときいたら、そうだと答えた。そこにつれあいもトイレから出てきて、テーブルについたのであるが、××はひたすらつれあいに向かい、熱心に、学生時代のあれやこれやをしゃべりまくっていた。それはつれあいはほとんど忘れていることのようだった。つれあいはこの再会にあきらかにショックを受けており、ショックを受けてるということを××にはひた隠しに隠していた。帰りの車の中でつれあいが言うには、「非論理的な頭で考えていたのだ、あの頃と同じような生き生きしたきびきびした若い女がやってくる、と」。それじゃ論理的な頭ではどう考えていたのかと聞くと、「ばかなことに、なんにも考えていなかった」と言った。××は、学生時代のことを、あの時代のことをかいておかなくちゃいけないと思うと強く主張し、今、回想録を書いているのだと言っていた。かいたら送るわね、みたいに言われて、あいまいに「ぜひ」とかなんとか言ってたつれあいであった。まあしかし、そのレストランのクラブケーキはおいしかった。蟹肉を少しのつなぎで豪華にまとめて、丸めて焼いた料理である。『検死官』シリーズ(舞台はまさにこのへん)にも出てくるクラブケーキ、ケイ・スカーペッタが、懇意の魚屋で、作り方も教えてもらいながら蟹肉を買うところが印象に残っている。 メリーランドの植物 2014年04月18日(金) つれあいが旧友に会いたいというので、Cに運転してもらって、あたしはいやいやついていった。チェサピークベイの向こう側(そこもメリーランド州)に行ったのだが、道々すごいものを見たのである。白い花の咲く、バラ科落葉高木で、満開であった。いい感じの上に伸びる木で大きすぎず小さすぎず、道路脇などにいかにも植えられたように生えていたが、そのうち、道路脇から逃げ出して林をつくり、いちめんの林になり、野生だったのかなと思うとまた道路脇などに植えられたみたいに生えていて、色もいろいろ、あるものは葉のない木にまっ白に花だけ咲いてるが、あるものは白い花に淡緑の葉がまじりこんでいて、あるものは淡緑の木の中に白い花が咲いているというぐあいで、つまり白から緑までグラデーションになってるのである。木は細長く、紡錘形をしており、幹は枝分かれをする。あれはなんだろうと話しながら向こうについて、土地の古老に聞いたところ、ホーソーン(サンザシ)だ、旺盛にいくらでも殖えるという。ホーソーンか、とうとう見たなどと思いつつも、なんか違う、サンザシというのはたしか藪状の灌木だったはず。で、帰ってきて、いつもの伝で調べ上げてるうちにたどりついたのが、Pyrus Calleryana 和名でマメナシないしはイヌナシという東アジア原産の植物。東海地方には自生地がいくつもあるそうだ。アジアナシの原種だそうだ。花は清楚で紅葉も美しく、観賞用の植物として手びろく植えられて(他にも使い道はあるようだ)まんまと逃げ出し、うち広がり、野山をおおい、今じゃこの辺で、invasiveな植物として扱われているそうだ。いやまったく、その広がり方は尋常じゃなかった。 ナショナルモール 2014年04月17日(木) ワシントンの町には、ナショナルモールなる大広場があって、国会議事堂からワシントン記念碑まで、まるまる見渡せる広大な芝生の大通りで、両側に豪壮な壮大な荘厳な建物がうち並び、それがスミソニアン博物館や国立ギャラリーや先住民博物館や歴史博物館や植物園などである。まず連想したのは、ウンター・デン・リンデンと博物館島。つくりがまったく同じで、豪壮さもよく似ている。俺様な感じも似ているし、虚勢張った感じもよく似ている。ロンドンのサウスケンジントンやトラファルガー広場のあたりともよく似ているが、ロンドンはもっと狭くてごちゃごちゃとある。もうすでに古いものがいっぱいあったから場所が取れなかったようだ。万博(1862)のあたりでいろんなものが揃えられるが、古いものはもっと古い。100年くらい古い、つまり18世紀に作りはじめられた印象。で、ベルリンはロンドンより少し新しい。20世紀にかかっているのもあって、鴎外のいたときには半分くらいはできてたが、あと半分はその後だ。そしてアメリカのはさらに新しい。広くて大きくて古めかしくて19世紀ヨーロッパの威勢をかたどっているけど、たいていのものは20世紀になってから作られている。ついこないだできたのもある。 花はさかりに 2014年04月17日(木) 月はくまなきをのみみるものかはといったって、こうまで散っちゃっちゃあ、花見とは言えないなという花見をしてきた。きのう空港の周囲で咲いてたのは正確にいえばサクラじゃなく他のバラ科落葉高木だったようだ。すごく寒かったが、きのうの雨で雲がぜんぶ吹き飛ばされて(花びらもすべて吹き飛ばされて)ぴーかんの青空。ジェファソン記念堂、ワシントン記念碑、リンカーン記念堂を遠くにみつつ(これは数年前に来たときじっくり見た)それから数々の美術館や博物館や植物園を回り抜いた。お昼は、先住民博物館で先住民食。バイソンステーキやワイルドライスや。Beech が花ざかり。いたるところで。ハナズオウも花ざかり。よく見たらマメ科だった。 ワシントン 2014年04月16日(水) ワシントンDC。マンチェスターから8時間だ。近い、近い。ものすごく楽だった。『河原荒草』に「待ってたら、待ってたへやが、そのままバスになって、動き出して、それから飛行機に、合体したよね、私はその乗り物を覚えていないのです」と書いたことがある。冒頭だ。そして最終章で「空港の待合室で待っていたら、待合室全体が動き出して、飛行機に合体しました」となるのだ。あれはもしかしたらワシントンのダレス空港のことだったのかも。ゲートから出て、たどりついた待合室で、待っていたら、その待合室全体が動き出して、合体した。飛行機じゃなくて、旅券審査場のある別の建物に。空港の敷地を、そういう待合室みたいな乗り物が何台も走っていた。P夫婦が迎えにきてくれて、Pの家に。途中はサクラだらけだった。満開のもあった。これから咲こうというのもあった。 あしたアメリカに帰る 2014年04月15日(火) 来たときには浅かった春が、いる間にどんどん深くなって今や春らんまんだ。明朝、空港にいき、車を返して、飛行機に乗る。ワシントンに寄って帰る。そこにつれあいの息子がいる。つまりこれはつれあい孝行の旅なのである。あと一息でうちに帰れる。ほんとは一刻も早く帰って、犬に会い、Mのクラスに出たいのだが。なにしろ、つれあい孝行の以下同文。グラスゴーから乗ってたのはVauxhallというイギリスでしかうってないらしい車の、Astraというスポーツタイプなコンパクト車。マニュアルに最初はびびったが、むしろこっちの方が車の動きがびんびん来て、清志郎の歌のようだ。こんど車買うときはマニュアル車に、と思わぬでもない。 ページ移動 / [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||