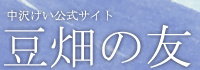|
|
 |
 |
| |
|
| |
ロンドンの金融街
2005年03月17日(木)
1985年の3月末、私はロンドンの金融街シティを歩いていました。ちょっと間抜けなのは、でかけたのが日曜日なので、あたりはがらんと静まり返っていたことでした。なんで、そんな場所を歩いていたのかというと小説のゆりかごを見ておこうと思ったのです。見てどうなるというものでもないのですが。
小説は19世紀の市民社会を背景に生まれた文学のひとつのジャンルです。教科書風に言えばそういうことになります。今でこそ、文学という言葉を小説作品と同じ意味に使う人も大勢いますが、小説というジャンルが登場するまえは、文学の主流は詩歌でした。印刷という技術がなければ小説は登場しなかったでしょう。また印刷された本を読むことができる読者がいなかければ、小説というジャンルが文学の主流になることもなかったでしょう。
市民社会を生み出したのはイギリスの産業革命とフランスの重商主義です。良識のボン・サンスはフランス語であるのに対してコモン・センスは常識と訳すことが多いのですが、最近良く耳にする市民感覚もたぶんもとはコモン・センスでしょう。ボン・サンスも個人の良識というよりは、市民に共通のよき感覚に近い言葉だと思います。
ええと、それで、イギリスの産業革命ですが、これは大きな資本を必要としたために、様々は金融の仕組みを生み出しました。と、ここまでは学校で習ったことですが、そうなると、ロンドンの金融街が小説のゆりかごのひとつであったことになるでしょう。風が吹けば桶屋が儲かるよりも、もう少し確実な事実だと思います。ま、そんなことをぼんやり考えながらとぼとぼ歩いてしました。旅行に行くと曜日の感覚をなくしてしまうので、日曜日だったのはまずかったなあと後悔。三島由紀夫の「絹と明察」とか高橋和己の「我が心は石にあらず」それにトーマス・マンの「ブッテンブローグ家の人々」なんて作品を思い浮かべていました。あと、イギリスの作家、デケンズの「クリスマルキャロル」とか「二都物語」なども浮かんできました。85年よりあとのことになりますが、安達裕美主演の「家なき子」といテレビドラマがはやった時、大江健三郎さんとドラマの話をしたら「あれはデケンズだよ」と言っていたのが印象に残っています。「同情するなら金をおくれ」のセリフが小学生に大流行でした。
シティはロンドンでも古い街で、日曜日でも日本風に言えば下町の感じが色濃く漂っていました。イギリスにしては珍しくいろいろなお魚を山積みにして売っている魚屋さんも近くにありました。その陳列の方法がまるで果物でも盛るように彩りよく魚を盛り上げて、なぜかそこにはうさぎもいて(食肉として売られているのです)色彩的なアクセントを付けるために、真っ赤なオマール海老がちらしてありました。
イースターが近づいていたために、お菓子屋さんは卵型のチョコレートでいっぱいでした。ものすごく豊富な種類の卵型チョコレートがありました。シティの近くのお菓子屋さんと魚屋さんで撮影した店先の様子は、今でも我が家の風呂場の脱衣場を飾る写真になっています。
その頃、もう、イギリスは「ウィンブルドン効果」と呼ばれる金融市場の外国への開放政策をとっていたのかどうか、調べてみたかったのですが、適当な資料が手元にありませんでした。「ウィンブルドン効果」というのはテニスのウィンブルドンのは世界中の選手が集まってくるように、金融市場を外国に開放して世界中の金融機関に集まってもらおうとする政策です。1985年はまたプラザ合意の年でもあって、そこから日本のバブル景気が始まるのです。今、振り返ってみると、現在、私たちが経験している変化はその時期から始まったものでした。パソコンならぬ自分で組み立てるコンピュター、「マイコン」が東京のデパートの売り場に出ていたころでした。
そんな変化の始まりとはつゆ知らず、うさぎと魚をいっしょに売っているのを私は珍しげに眺めていました。日本の兜町や証券取引所のほうがロンドンをまねたのでしょうけれども、似たような下町にあるのもちょっと意外な感じがしました。
↓前の日記
/ 次の日記↑
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|