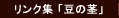|
|
 |
 |
| |
|
| |
月光洞建設計画2
2010年08月17日(火)

↓

長い間止まっていた月光洞建設計画ですが、2010年3月に土地を取得しました。
夏になって、草ぼうぼうになっていた土地の草刈を両総管理の森社長がして下さいました。道の向こうに広がっている水田では、そろそろ稲穂が出る頃でしょうか?
房総半島では8月末になるともう稲刈りが始まります。9月には房総の新米が、我が家の近くのスーパーにも袋詰めされて並びます。
月光洞建設計画1
2006年09月13日(水)
建築家の鈴木隆之氏に家の設計をしてもらっています。現在、小学館の「本の窓」でその計画について鈴木氏と共同で「田舎に家を建てる」を連載中です。このトピックスでは「本の窓」連載には盛り込め切れなった話を少しづつ書いて行きます。
鈴木隆之氏は1987年に「ポートレイト・イン・ナンバー」で第三十回群像新人賞小説部門受賞者。私は第二十一回の群像新人賞受賞者なので、群像新人賞の受賞パーティでよくお目にかかっていました。
家を建てる話も最初は群像新人賞受賞パーティの雑談からでした。
月光洞はこれまで敷地が大原の下布施にあるところから下布施の家とか施主(なぜか建築のクライアントはこう呼ばれます)の私が小説家なので小説家の家などと呼ばれてきましたが、06年8月末に「月光洞」と命名しました。

写真は鈴木隆之氏が家のイメージを銅版に打ち出したものです。またこの建築計画はSDレビュー2006のコンペテンションに入賞しています。
【リンク】
・SDレビュー2006
建築・環境・インテリアのドローイングと模型の入選展
・鈴木隆之氏のホームページ
「雨の日と青い鳥」朗読会バージョン
2006年07月19日(水)
 「豊海と育海の物語」(集英社文庫)を書くきっかけになった「光村図書 国語2(中学2年生用教科書)」の書き下ろし作品「雨の日と青い鳥」をアップします。ただし、ここにアップするのは教科書そのままではなく、昨年の「豆畑の朗読会」第一回で読んだ朗読会バージョンです。教科書ではさまざまな配慮や制約があるために、削除された表現があります。朗読会バージョンのほうはそうした削除された表現を復活させるかたちになっています。 「豊海と育海の物語」(集英社文庫)を書くきっかけになった「光村図書 国語2(中学2年生用教科書)」の書き下ろし作品「雨の日と青い鳥」をアップします。ただし、ここにアップするのは教科書そのままではなく、昨年の「豆畑の朗読会」第一回で読んだ朗読会バージョンです。教科書ではさまざまな配慮や制約があるために、削除された表現があります。朗読会バージョンのほうはそうした削除された表現を復活させるかたちになっています。
「雨の日と青い鳥」
朝から雨が降っていた。春の雨は土のにおいがする。アスファルトで固められた道を歩いていても、春の海は黒い土のにおいがした。花の球根や野菜の種を優しく包んでいる土のにおいだ。育海はスカートのすそに泥はねが付く雨の日が好きではない。けれども、黒い土のにおいをかぐのは好きだった。
育てる海と書いて「いくみ」と読む。宇野の好きな両親がつけた名前だ。新学期になると、いつも、先生から名前の読み方を質問される。今年も、新しく教科を担当する先生たちに名前の読み方を尋ねられた。理科の大和田先生は
「ほう、『いくみ』と読むの。君は、お兄ちゃんがいるだろう。豊かな海と書いて『とよみ』と読むお兄ちゃんがいるね。」
と言った。大和田先生は豊海のことをよく覚えていた。
「豊海君にはこんなかわいい妹がいたんだ。」
と感心したようににこにこしながら、出席簿をぱたんと閉じた。
豊海と育海は年子の兄と妹だ。豊海は二月生まれ。育海は9月生まれだから、年は一つしか違わないが、学年は二つ違った。豊海はこの春、高校生になった。中学二年生になった育海は、先生たちに名前を尋ねられる一週が過ぎて、ほっとしたところだ。自分の名前は好きだけれども、クラスのみんなの前で答えるときは緊張してしまう。ほっとしたところで兄ちゃんとけんかをした。今朝のことだ。
街の中で黒い土のにおいをかぎながら、あんな兄ちゃんなんて大きらいだと、育海はふくれっつらだった。雨はやまない。学校から帰って、本町の栄光堂書店に育海が行こうとしたときも、細くて白い雨は降っていた。道路も車も港も船も、そして魚市場も、みんな白い雨の中に煙っていた。 今朝、豊海は妹に、学校が終わったら栄光堂書店い行って模擬テストの申し込みをしてきてくれと頼んだ。兄ちゃんは頼んだと言うけれども、あれは頼むというよりも命令だと、育海はおもしろくない。育海の模擬テストの申し込みもあったから、ついでに手続きをするのはなんでもない。でも、兄ちゃんの言い方が横暴だった、だから豊海に言ってやった。「いやだ。自分で行けばいいでしょ。」
兄ちゃんは
「おれ、部活があるもん。」
なんて言い訳をした。新入生に部活動なんてあるわけがない。
「一年坊主のくせに、すぐばれるうそが言えるじゃん。」
豊海は妹に言い返す言葉がない。しばらく不愉快そうに口を閉じていた。それから、にっと笑った。
「おれ、部活の見学なんだ。だから、テストの申し込みに行ってくれよ。」
早口にそう言った。にっと笑った顔で、部活の見学なんて口実だとわかってしまう。雨が降っているから面倒くさいのだと育海は思った。栄光堂書店のある本町は、高校生が通学に使う電車の駅よりも港に近い。雨降りだから自転車も使えず、歩いて本町まで回るのがいやなだけだと育海は決めつけた。「行け。」「いやだ。」の応酬はたちまち口論となり、兄ちゃんが妹をののしるから、育海も思い切り悪口を言ってやった。
栄光堂書店のレジで育海は申し込みをするかどうか迷った。そして、気がついた。兄ちゃんは受験料を渡してくれなかった。けんかで受験料どころではなかったのだ。
港では雨の中で、並んだ漁船がしょんぼりしていた。自分のテストの申し込みだけをした育海は、MDに録音した好きな音楽を聞きながら歩いた。港の雨は魚のにおいがした。新鮮な魚のにおいがした。魚市場は荷を揚げる船もなくて閑散としていた。受験料なしに、どやって申し込みをしろというのだろう。育海は兄ちゃんにそう言ってやろうと思っていた。雨のために空と海の区別がつなかい。港の入り口の赤灯台、白灯台がおたがいそっぽを向くように建っていた。海は広々している。
家に帰ると、電話が鳴っていたような気がした。育海はMDのスイッチを切り、電話機を見つめた。じっと見たからといって、電話機が「はい、鳴っていましたよ」と答えるはずがない。気のせいかもしれないい。育海はウィンド・ブレーカーを脱ぎかけた。とたんに電話が鳴った。
「あ、育海、もしもし、育海だろ。」
兄ちゃんだった。携帯電話からかけているらしい。育海はきっと模擬テストのことだと思った。携帯電話の音声はとぎれがちで、豊海が何を言っているのか、よく聞き取れない。
「だから、そうじゃなくて、鳥がね。そう、鳥だよ。鳥が落ちていたんだ。」
兄ちゃんは大きな声を出していた。いくら大きな声を出しても、ガアガアいう雑音には勝てない。
「かご、かご、かごがあるだろ。」
という兄ちゃんの声を最後に電話はぷつりと切れてしまった。豊海は朝の口論のことなどすっかり忘れているようすだった。
「鳥が落ちていたんだって。」
育海はだれもいない家の中で、声に出して、そう言ってから、肩をすくめた。お父さんは水産加工の会社に、お母さんは漁業協同組合に勤めていたから、二人は保育園に通っていた。保育園のころを知っている人は、口をそろえて仲良しの兄妹だったと言う。でも育海にはそれが信じられない。
兄ちゃんはずるい。保育園のころは兄ちゃんだけ年が一つ多いのも、ずるいと思っていた。誕生日が来て、もう少しで兄ちゃんと同じ年になれると楽しみにしていると、兄ちゃんも一つ年が増えて、また差が開くのが納得できなかった。さすがに、もう、どうして兄ちゃんは同じ年になるまで待ってくれないのだろうとは思わなくなったが、今は兄ちゃんの横暴に腹が立つ。横暴で、乱暴でそのうえ面倒くさがり屋だ。
それにしても、兄ちゃんは、いったい、どんな鳥を拾ったのだろう。新しい制服のネクタイをよれよれにした兄ちゃんが、とさかの立派なおんどりを小わきに抱えて、玄関に立っている姿が浮かんで、思わず笑い出したくなる。
でも、笑い事ではない。兄ちゃんが生き物を家に持ってきたために起きた騒動は幾つもある。理科の大和田先生がよく覚えているわけだ。中でも、カマキリ騒動はひどかった。家の中が暖かかったために、真冬の夜中にカマキリの卵が孵化してしまった。兄ちゃんが拾ってきた卵だった。いっしょの部屋で寝ていた育海、ぞろぞろうまれてくるカマキリの赤ちゃんに悲鳴をあげた。育海は虫がきらいだ。兄ちゃんはおろおろするばかりだった。掃除機をかついだお母さんがぱっと現れて、カマキリの赤ちゃんを吸い込んでくれなければ、いったいどうなったのだろう。カマキリ騒動以来、育海は豊海と別の部屋に寝起きをするようになった。兄ちゃんは面倒くさがり屋なにに、どうして次から次へと生き物を家に運んでくるのだろう。
豊海が拾ってきたのは、水色のセキセイインコだった。
「育海、かごだ。かごを持ってこい。」
兄ちゃんの言い方はやっぱり命令口調だ。鳥は震えている。首の周りの羽根が抜けて、地肌があらわになっていた。みすぼらしいのは、雨にぬれたせいでもあった。育海はしぶしぶ物置に行った。兄ちゃんの命令は無視したいとろこだけど、鳥があんまり情けない姿をしているのは見ていたくなかった。物置には兄ちゃんが言ったとおり、鳥かごがあった。ほこりだらけだった。育海はおふろ場で鳥かごを洗う。洗いながら「面倒くさい仕事はいつもあたし」と一人で文句を言っていた。
「兄ちゃん、この鳥をどこで拾ったの。」
豊海は洗いたての鳥かごにインコを入れた。鳥しか入っていないかごは寒々しい。
「兄ちゃんってよぶなって言ったろ。」
かごに入れた鳥の様子を見るので夢中な豊海はぶっきらぼうに言う。
「じゃあ、何と言えばいいの。」
鳥はかごの片隅にうずくまった。止まり木に止まる元気はないらしい。羽根の中に頭をうずめようとするのだが、首の回りの羽根がないので、うまく頭をうずめられない。
「お兄さんと言え。お兄さんと。駅の裏で拾ったんだ。きっとだれか飼い主がいる鳥だよ。逃げちゃったんだね。たぶん。」
豊海は鳥かごにぼろきれを入れた。
「体が冷たい。温めてやらないと。」
ぼろきれで囲まれた鳥はおびえていた。豊海の親切が鳥にとっては恐怖を覚えさせるらしい。鳥はまばたきを繰り返した。
「温める方法はないかな。ストーブをたこうか。手の中で温めてやるのがいいのかな。」
うずくまったままの鳥に、豊海がやたらにぼろきれを掛けようとした。
「お医者さんにみせたら。」
「鳥のお医者さんなんて、どこにいるんだい。」
豊海の声は途方に暮れた響きがあった。それでも豊海は熱心に鳥かごをのぞき込んでいた。育海が熱をだしたとき、そんなふうに兄ちゃんにじっと見つめられたことがあった。いつもは育海が風邪で熱をだしても、無頓着でテレビを見て笑っている豊海だった。その晩は「いいかい、心配しないでいいよ。」と豊海も言った。育海は七つだった。豊海がいつになく真剣なのが、育海にはおかしかった。育海の額に冷たいタオルを乗せてから、豊海は地区の集会にでているお母さんを呼び戻しに夜の道を走った。後から育海の熱は風邪ではなくて、溶連菌感染症といういかめしい名前の病気だとわかって、家じゅうで驚いた。
育海の異変を豊海が最初に見抜いたときのことをひょいと思い出すと、彼女は優しい気持ちになった。優しい気持ちになると知恵がわいた。育海は電話帳で「獣医」の項目を引いてみた。家の近くに獣医さんは五人いた。育海は片っ端から電話をしてみることにした。一軒目は「豚や牛が専門だから。」と断られた。二軒目は電話に出なかった。三軒目の電話番号は豊海が読み上げた。若い男の人が出た。「すぐに連れてきなさい」という返事をくれた。
雨はさすがに小やみになっていた。夜の海がゆっくりとうねる海岸通りを豊海と育海は急いだ。鳥を冷たい風に当てないように、かご全体をバスタオルでくるんで豊海が抱えていた。電話で教えられた通り、港から本町へ出る坂を上っていくと、小暗い中に明かりの漏れている家が一軒だけあった。病院というより、八百屋かお菓子屋のような家の戸をたたくと、ぼさぼさ頭の男の人が戸を開けてくれた。それが電話に出た獣医さんだった。電話の声のほうが実物よりも若い感じがしたと育海は思った。
豊海の話を聞きながら、ひととおりの診察を済ませた獣医さんは、鳥かごに戻したインコの様子を見ながら言った。
「へえ、拾ったの。」
鳥はまたかごの片隅にうずくまる。まぶたを閉じてじっとしていた。腹の辺りがかすかに動いている。うずくまると、首の付け根の羽根がないのがよけいに痛々しかった。
「僕も、ずいぶんいろんな生き物を拾ったなあ。拾って面倒をみたんだ。でも、中にはだめだったのもあった。巣から落ちた幼いすずめなんて、えさをやるだけでも難しくてね。朝になったら冷たくなっていたこともあったし、本当に小さな命はすぐに消えることがあるんだね。ちょっとしたことが命取りだ。」
獣医さんは感慨深そうに言った。話を聞いている二人には、獣医さんには獣医さんのさまざまな思い出があるとはわからないから、命取りという言葉だけが耳に残って、急速に不安がふくらんだ。二人の顔を見た獣医さんは、ぼさぼさの頭をかきながら笑った。
「大丈夫。いや、命のことであんまり感傷的になるのは命に失礼だったね。こんな成鳥になった鳥はそう簡単に命を落としたりしないよ。良いお薬を出しましょう。飲み水に混ぜて飲ませてください。すぐに良くなるよ。お大事に」
獣医さんは奥に薬を取りに行った。育海が診察料の心配を小声で豊海に話した。すると豊海は「お母さんからもらった模擬試験の受験料があるよ。僕は一年坊主だから、まだ受けなくてもいいんだ」と耳打ちした。二年生の育海は兄ちゃんの「一年坊主」という言葉ににんまりした。
「この鳥、手乗りだからかわいがられて育ったんだろうね。」
兄ちゃんは止まり木止まれるようになった鳥に手を差し出しては、自分の指に止まらせていた。「迷子の鳥 預かっています」のポスターを自分で作って、駅の裏のあっちこっちにはったくせに、鳥に向かって「おまえ、ずっとここにいろよ。」と話しかけていた。育海は、首の回りの羽根が肌を突き破るように生えてきたのを少し気持ち悪く眺めている。そして「また兄ちゃんとけんかをするのだろうな。」とひそかに思っていた。
↑前のページ / ↓次のページ
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|
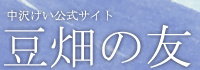




























































































 豆ちゃんは「じゃあ、僕、バージンブルースを歌いましょうか」なんて言い出しました。と言うわけで第二回朗読会の幕開けは豆ちゃんの歌。「月のひざし」と「バージンブルース」です。野坂昭如の「バージンブルース」なんて言ってまいしたが、けっこう可愛い声で歌っていて、野坂昭如というより秋吉久美子。あとで聞いたら戸川純で覚えた「バージンブルース」がそうです。
豆ちゃんは「じゃあ、僕、バージンブルースを歌いましょうか」なんて言い出しました。と言うわけで第二回朗読会の幕開けは豆ちゃんの歌。「月のひざし」と「バージンブルース」です。野坂昭如の「バージンブルース」なんて言ってまいしたが、けっこう可愛い声で歌っていて、野坂昭如というより秋吉久美子。あとで聞いたら戸川純で覚えた「バージンブルース」がそうです。 最初にお互いの作品を入れ違えて読み、それから、自分の作品を読むという方法は、外国の作家とのシンポジウムなどで使います。今回の朗読会でもその方法を使うことにしました。シンポジウムでは、お互いの言葉の響きが理解できるようにという目的で双方の作品を入れ違えて読むのです。この場合、お互いに翻訳された作品である場合がほとんどで、音はわかるけれども意味は解りません。今回は、そうは行かない! 伊藤さんは詩人としての出発からずっと朗読会をやっているのです。「日本の作家が自分の作品を読むのなんて聞いたことがない」って言ってましたが、私は外国の作家とのシンポジウムなどで、便宜的に自作を朗読することがあるだけで、伊藤さんのように観衆の前で朗読なんてほとんどしたことがありません。つまり競争にも何もならないのです。
最初にお互いの作品を入れ違えて読み、それから、自分の作品を読むという方法は、外国の作家とのシンポジウムなどで使います。今回の朗読会でもその方法を使うことにしました。シンポジウムでは、お互いの言葉の響きが理解できるようにという目的で双方の作品を入れ違えて読むのです。この場合、お互いに翻訳された作品である場合がほとんどで、音はわかるけれども意味は解りません。今回は、そうは行かない! 伊藤さんは詩人としての出発からずっと朗読会をやっているのです。「日本の作家が自分の作品を読むのなんて聞いたことがない」って言ってましたが、私は外国の作家とのシンポジウムなどで、便宜的に自作を朗読することがあるだけで、伊藤さんのように観衆の前で朗読なんてほとんどしたことがありません。つまり競争にも何もならないのです。
 朗読会では「うさぎ狩り」を読む前にMr.チルドレンの「隔たり」という曲を親子で聴いてしまったという話をしたのですが、ここでは別の話を書きます。森鴎外の奥さんで森しげという人がいます。この人は森茉莉さんのお母さんです。鴎外に進められて小説を書いています。森しげの作品に新婚の夫が避妊をしたので侮辱されたと感じたという短編があります。(ごめんなさい。これもあとでちゃんとタイトルを入れます)日本の社会にはちょっと前までは玄人と素人の区別があって、婚姻外の男女関係を見るまなざしが険しかったという事情があります。森しげの小説はそのあたりの微妙な感覚が出ているのでよく記憶していました。医学者としての鴎外の考えとお嬢さんから人妻になったばかりの奥さんの感じ方が食い違ってしまうのも無理がないところがあります。もともと、素人と玄人を区別するようなベースのあったところに、敗戦のショックが来て、ますます話がこんがらがった挙句に、豆ちゃんが歌った「バージンブルース」の頃には若い娘が玄人みたいな振る舞いをするというけわしい目と、自由になっていいなあとやっかんだり羨んだりする目が交錯していました。「神田川」とか漫画の「同棲時代」というような同棲を扱ったやや暗め、いや、ものすごく暗いものが大流行だったのがその時代です。
朗読会では「うさぎ狩り」を読む前にMr.チルドレンの「隔たり」という曲を親子で聴いてしまったという話をしたのですが、ここでは別の話を書きます。森鴎外の奥さんで森しげという人がいます。この人は森茉莉さんのお母さんです。鴎外に進められて小説を書いています。森しげの作品に新婚の夫が避妊をしたので侮辱されたと感じたという短編があります。(ごめんなさい。これもあとでちゃんとタイトルを入れます)日本の社会にはちょっと前までは玄人と素人の区別があって、婚姻外の男女関係を見るまなざしが険しかったという事情があります。森しげの小説はそのあたりの微妙な感覚が出ているのでよく記憶していました。医学者としての鴎外の考えとお嬢さんから人妻になったばかりの奥さんの感じ方が食い違ってしまうのも無理がないところがあります。もともと、素人と玄人を区別するようなベースのあったところに、敗戦のショックが来て、ますます話がこんがらがった挙句に、豆ちゃんが歌った「バージンブルース」の頃には若い娘が玄人みたいな振る舞いをするというけわしい目と、自由になっていいなあとやっかんだり羨んだりする目が交錯していました。「神田川」とか漫画の「同棲時代」というような同棲を扱ったやや暗め、いや、ものすごく暗いものが大流行だったのがその時代です。 で、最後は大鉈をかついだ伊藤さんの朗読です。読むのはもちろん高見順賞の受賞作の「河原荒草」から「道行き」です。です。2時間は私にとってはあっと言うまでした。あとの小宴で「股間で鳴いていたのは油蝉かつくつく法師か」と聞かれでまたおお焦りでした。
で、最後は大鉈をかついだ伊藤さんの朗読です。読むのはもちろん高見順賞の受賞作の「河原荒草」から「道行き」です。です。2時間は私にとってはあっと言うまでした。あとの小宴で「股間で鳴いていたのは油蝉かつくつく法師か」と聞かれでまたおお焦りでした。