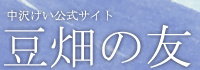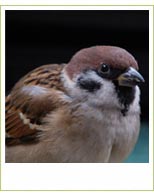|
|
 |
 |
| |
|
| |
納棺師さん
2012年04月18日(水)
二人組の女の納棺師さんたちがやってきた。手順はマニュアルどおりで、ついこないだも、あたしはマニュアルどおりに訓練される日本の若いものたちや企業をさんざん批判していたのだが、このマニュアルらしさは死者や遺族に対する距離がよく取れて、なかなか心地のよいマニュアルであった。ひとりがさかんに動く間、もうひとりが手伝いながら、共感をこめた笑顔をみせてくれて、いろいろ話しかけてくれ、またこちらの問いにも答えてくれ、そこはマニュアルではなく臨機応変の人間らしさがあふれていた。
前日の父はまだ人間の父であった。しかし病院に行く直前の父は、おどろくほど老い衰えた、顔だちも、表情も、人格さえもかわってしまった父であった。死ぬときは顔色が悪く、死ぬちょっと前から死体の顔色をしていた。息をふたつした。それであたしには息がとまったのが見えた。あれ、と思ったらときにK先生が駆け込んできて、伊藤さん息してらっしゃいませんよ、心臓は動いてますけど、といって、脈をみた。その日朝入院したときに、延命のための手段は一切しないと話し合ってあったから、そういうことは何もなかった。ひろみさん、手をにぎってと先生にいわれた。にぎると脈うっているのがわかった。そして先生もあたしも、ただ脈を感じて、機械の音をききつづけた。先生のうしろにTさんがいた。「とげ抜き」に出てきた、母に巣鴨の話をよくしてくれた婦長さん(むかしでいえば)だ。三人で父をみつめた。やがて機械の音が単調になった。先生が目の中をのぞきこんで時計をみた。そのときにはもう手の中の脈はなくなっていた。そのときはただ父がそこにいた。先生とTさんがあたしを父とふたりにしてくれた。「おとうさんありがとう」というのが、ほんとに陳腐ではあるが、まず口に出たことばだった。「ほんとにありがとう」と。理由はいろいろある。なにしろあたしはしめきりがあって、それをまず終えてきますといって病院を出てうちで仕事していたのだ。何時間もかかって、夕方になってやっと終わって、病院にかけもどった。そのほんの10分後である。先生といろんなことを相談して病室にもどった2分後のことである。死んだ父はしずかで動かなかったが、体温があった。いつものままだった。
つぎの日になると、口があいた。いわゆる死に顔になっていた。そこで話は納棺師さんにもどる。かれらが口に綿をつめたり化粧をしてくれたりしている間に、だんだん父がもどってきた。父の顔色も、表情ももどってきたし、そしたら、あのここ数週間の、機嫌のわるい、かなきり声をあげる、頭の働きも心の働きも後退した父が、どんどん遠ざかっていくような気がした。
↓前の日記
/ 次の日記↑
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|