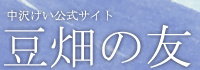|
|
 |
 |
| |
|
| |
手が書く
2006年08月13日(日)
フードジャーナリスト、というよりもエッセイストと言ったほうがいいかもしれませんが、平松洋子さんにお目にかかった話は以前、ここに書きました。現在、発売中の「表現者」8月号にインタビューが掲載されています。平松さんとのお話の中で「手が書く」ということがでてきました。「手が書くのを頭が追いかけるくらいがちょうど良い」という話です。
手が書くというのは、平松さんのエッセイを読んでいるとお料理のレシピがしぜんに伝わってきて、お料理が出来てしまうということから出てきた話です。身体で覚えこんで納得したことを書くという意味です。例えば水餃子などは、納得が行くまで毎朝、自分で作った結果でエッセイを書いているから、読んだだけで、自然に餃子の皮つくりができるのです。この「手が書く」文章が美しいというのは昭和の文学が生み出した最大の美学だったと私は思います。
私小説がよく読まれ、またよく書かれたのは、頭で考えて書くのではなく、肉体に刻み込まれたものを「手が書き」それを「頭が追いかける」という作業を追及した結果だったと言えるでしょう。文語文から美文へそして口語文への流れの中で、文学は欧米の文学の模倣をしなければならなかった結果として、より身体化された言葉を求める流れが出てきたのでした。その良き結果が、平松洋子さんのエッセイに現れているということになります。
水餃子やキムチならそれで良いとして、これが人殺しになると、身体で納得して書くというのはたいへん無謀なことになります。小説家として言えば、一方では身体的な納得のある文章を求められながら、また一方ではとうてい個人としては体験しえない、あるいは体験してはならないテーマを描かなければならないというジレンマを昭和の終わりの作家は背負っていたという感慨を思えます。島田雅彦や松浦理英子さんの仕事には、扱うテーマは違ってもそうしたジレンマを感じさせられるものがたくさんあります。「手が書く」という美意識の限界点での悪戦苦闘はそこにはあるわけです。
現在、私小説の延長の仕事をしようとしている作家が何人かいますが、それらの人々は「手が書く」ということの延長で、文章の美意識を磨いているかというと、そうではないような気がしています。それよりはプライベートな感情を書くことに魅力を見ているのではないでしょうか?一口にプライベートな感情を書くと言ってもそのスタンスはいろいろであることは言うまでもありません。が、「手が書く」という美意識とはひとまず切り離されているということをここでは書きたかったのです。
来年、静岡新聞で、歴史小説を連載するために遠藤周作の作品を纏めてよんでいます。生前、遠藤さんは日本の文学が「手が書く」私小説に占領されていたことを嘆いていたと聞いています。広い意味での戦後の文学というものは、個々の作品としては読んでいても、全体の流れを自分なりの体系の中をおき直すことが出来ませんでしたが、「手が書く」という美意識の臨界点での戦いというイメージを持つと、何かが少し整理できるような光を見出しています。
↓前の日記
/ 次の日記↑
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|