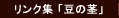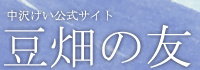 |
||||
その時々の話題を提供するトピックスです。私の仕事に限らずリンクを張っていただいている皆さんともいろいろなイベントをこのトピックス欄を使ってやって行きたいを思っています。良いアイディアがあったらぜひご提案ください。お待ちしてます。 |
| タイトル一覧 |
| 最新の10件 |
| ログ検索 |
| 管理者用 |
|
さよなら「子ども」たち〜「楽隊のうさぎ」を読んで 2005年02月03日(木)
太平洋プロジェクト・寶洋平 中沢けい「楽隊のうさぎ」を読んでいるあいだずっと、胸のなかになにかあたたかいものがいた。もしやうさぎが棲みついたのか? なんて思っていたのだが、読み終えてしばらくしてわかった。充足感だ。それはいまもまだ、たっぷりと残っている。 主人公の少年、奥田克久は中学でブラスバンド部に入る。ちょっとドジで、小学生の頃いじめられた経験から何かあると心を閉ざしてしまう癖をもっている。だが、あるとき近所の花の木公園で見かけて以来胸に棲みついたうさぎが、粗野な同級生から嫌がらせを受ける局面で現れるようになり、ピンチを軽やかに切り抜けるための助言をくれる。時にはうさぎに助けられながら、ブラスバンド部の練習、同じ仲間や先生、両親との関わりをとおして強くなっていく克久。そしてブラスバンド部は全国コンクールに出場、本番で楽曲の最初と最後を飾るティンパニの担当をした克久は、演奏を成功に導いていく。――そんな話だ。 新潮文庫の勝又浩の解説によれば、ブラスバンド部の中高生やその両親を中心に広く読まれているという。うなずける。明晰な文章で隅々まで詳しく描かれていて、登場人物や起こる出来事がリアルだからだ。実際、ネット上にブラスバンド部の中高生や、その両親だとわかる読者からの感想の書きこみが散見される。 ただ、そのように「ブラスバンド」小説として思う存分堪能できるこの作品は、実はそうした枠からはみ出たところの豊かさを問題にすべき種類の作品であるように思える。冒頭に書いた「充足感」は、この小説の底に流れるある切実で過剰な力がもたらしたものだと私は考えている。作品内に「今じゃなければできない演奏がある」という言葉が出てくるが、この作品こそ中沢けいのそういう種類の仕事だったのではあるまいか、直感的にそう思った。 過剰な力とは? それを知るために、中沢けいの小説を書くスタイルについて改めて確認しておきたい。中沢けいは知的な作家だと考えられていて、それはもちろん正しい。ただ、ここで知性というのは、外来の新しいものにいち早く反応して整理したりアレンジして取り出してみせることを指すのではなく、自らの身体感覚、つまり実感ベースで捉えた世界を構築していくという意味である。だからむしろ、世界に腰を据えたうえで全身を使って小説を書いている、と考えたほうが理解しやすい。このスタイルは、ただでさえ破綻を抱えながら日々更新し続けていくこの社会を大げさに糾弾したり破壊してみせたりするのではなくその反対で、そうした社会を引き受けたうえで実感に基づいた価値観を提示するベクトルに向かう。中沢けいの作品のなかに流行語とか固有名詞が出てきたり、新奇な素材が扱われることはほとんどないが、読めば必ず「現在」の社会の空気が立ち上がってくるのは、この態度によるものが大きいだろう。 一つ、例を挙げる。中沢けいはしばしば、母親を「女親」、父親を「男親」と表現してきた。そうすることで、父、母という役割の固定観念を切り崩しながら、「親になった女」「親になった男」からの視点を獲得している。近代社会の最小構成単位とされる「父」と「母」と「子」が、中沢の小説世界にあっては「親になった男」と「親になった女」と「子」として描かれる。実感ベースで捉えた世界を構築していくというのは、そういうことだ。 このことを確かめたうえで「楽隊のうさぎ」のなかでとりわけ印象的だった場面を見てみる。克久が中学二年の夏休み、母親である百合子が自分の陶器店の買い付けを兼ね、福岡の実家に克久に旅行へ行くことを提案する。が、克久はブラスバンド部の練習があるから行けないのだと答え、言い合いになる。なかなか折れない百合子は子どものようにむくれた顔で横を向いたりして、克久はそんな母親のふるまいをまるで周囲の女の子のようだと感じて困惑する。このときの百合子の女親としての心理を引用。 それでも、百合子には、この夏を過ぎたら、子どもらしい克久を連れて歩くことはできそうにない予感があった。……中略……春を待っていたら、子どもらしい克久の面影はすっかり消え失せているかもしれない。 かつては子どもらしい「子」だったはずの克久と一緒にいられる時間に「終わり」が来ようとしている。十四歳といえば、その「終わり」とは何よりもまず身体の成長によって起こるものだろうし、また、ブラスバンドのような自分のフィールドを見出したことによって一個人としての都合が出てくることでもあるだろう。この「終わり」に、誰も抗うことはできない。そして同時にそれは前述した「親になった女」「親になった男」からの視点にも、ある決定的な変化が起こらざるを得ないことを意味している。「楽隊のうさぎ」が基本的には克久の視点から語られながらゆるやかにその母親である百合子に移ってゆくのも、この「終わり」と深い結びつきがある。おそらく、この小説は中沢けいにとって、親の視点から子どもらしい「子」を描き得る最後の作品なのだ。切実で過剰な力。それは「子」の「終わり」を意識した「親になった男」「親になった女」から送られた、「子」に対する過剰なまでに強い愛情であり、メッセージである。「楽隊のうさぎ」を読んでそれをたっぷりと受け取ることができる私たち読者は、ほんとうに幸せだ。 寶洋平さんの太平洋プロジェクトはこちら。 |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||