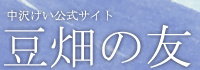|
|
 |
 |
| |
|
| |
島尾敏雄 小川国夫 吉田健一
2014年11月30日(日)
島尾敏雄の「死の棘」は一般には夫婦間の激しい諍いの繰り返しを描いた狂気の小説として読まれている。が、あれは戦争のもっとも悲惨な後遺症を描いたものではないかと考えている。ひとつの国の国民がすべからく「死」を意識し、しかも「永遠」をなんらかのかたちで身近に引き寄せた時、そこで時間は垂直方向へ伸びて行く。そこでは永遠という時間は、才能に恵まれた詩人のインスピレーションの源ではなく、ごく平凡な俗世を生きる人々共通の体験となる。この体験は戦争が終わり人々が日常を取り戻した時、垂直の時間は横倒しとなり、横倒しとなった永遠は日常生活で「反復」の恐怖を生む。
島尾敏雄は「出発をついに訪れず」「魚雷艇学生」などの作品で知られる。いずれも海軍の魚雷艇「震洋」の特講隊長として出撃命令を受けながら、8月15日の終戦を迎え、ついに発進の命令はなかったことの顛末を描いた作品である。妻との争いを描いた「死の棘」の系列の作品と、魚雷艇特講隊長の体験を描いた作品は別の系列と作品群とされることが多いが、この二つの作品群は根本のところで、垂直であった永遠の時間が横倒しになるという繋がりを持っている。奄美群島加計呂麻島で生まれたロマンス(妻との出会い)。二人の恋は、男が永遠の彼方にはかなくも終わりを迎えるはずであったのに、戦争の終結はその後の日常に長い反復の争いをもたらす。小川国夫は近代文学辞典(講談社)の「島尾敏雄」の項目で、「死の棘」の二人の出会いに「死」があったことを指摘している。その指摘を待つまでもなく小説のタイトル自体が聖書からとられた「死の棘」という言葉であるところにそれはもう現れていると言えるだろう。
なかなか抜けない「死の棘」に刺されていたのは、島尾敏雄夫妻ばかりではない。戦争を体験したすべての人々は多かれ少なかれ精神に「死の棘」が刺さっていたと言っていいだろう。本来、垂直なものとしてイメージされる時間が、横倒しとなり、そこでは日常は永遠の反復を繰り返す。
小川国夫の私家版「アポロンの島」を最初に高く評価したのは島尾敏雄だった。「アポロンの島」に描かれた日常の中に屹立する永遠の光景を島尾敏雄は直截に受け止め、高い評価を与えた。同じ日常の反復でも、月並み屏風に見られるような、あるいは歳時記にみられるような健全な豊かさを備えた日常の反復を愛し、そのに流れる時間を創造したのは吉田健一であろう。横倒しになった永遠を生きざる負えなかった島尾敏雄と、垂直の時間を見た小川国夫と、豊かに流れる日常の時間を創造した吉田健一、そのように並べて眺めてみることに興味を感じている。
明日から12月。小川国夫さんは12月21日のお生まれだったので、年末になると静岡へお誕生日の会へうかがっていた。小川さんのとご縁は1995年1月にご本人から静岡へ講演に来ないかと誘っていただく電話があった時以来。阪神大震災で騒然としている時だった。
↓前の日記
/ 次の日記↑
|
| |
|
|
|
|
| |
|
| |
|